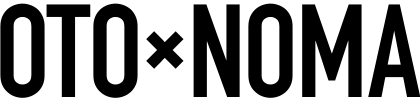壮大なサウンドも思いのまま!オーケストレーション上達10のヒケツ!!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介(@Ken_Inage)です。
OTOxNOMAメンバーさんの中には、
「オーケストレーションが上手くなりたい!!」
という方も少なくないかと思います。
そんなわけで今日は、オーケストレーション上達のための10のヒケツについて詳しく解説していこうと思います。
とくに、劇伴やゲーム音楽などのBGMを作りたい人は必見ですよ!
オーケストレーション上達10のヒケツ!!

今日ご紹介するオーケストレーション上達10のヒケツは以下の通りです。
- 和声学を学ぶ
- 楽器法を学ぶ
- 管弦楽法を学ぶ
- スコアを片っ端から分析する
- 生のオーケストラを聴きにいく
- 奏者さんの友達を作る
- 管弦打楽器すべて一通りさわってみる
- オーケストラ&吹奏楽団に入団する
- 指揮を経験する
- レコーディングで大失敗する
それぞれ詳しく解説していきます!
オーケストレーション上達10のヒケツ
①和声学ぶ
②楽器法学ぶ
③管弦楽法学ぶ
④スコア片っ端から分析
⑤管弦打一通り楽器触ってみる
⑤奏者さんの友達作る
⑦生オケ聞きにいく
⑧オケor吹奏楽団に入る
⑨指揮を経験する
⑩レコーディングで大失敗するとくに最後のは一番学べます!マジです。
— 作曲家・稲毛謙介(イナゲケンスケ) (@Ken_Inage) April 6, 2020
STEP1:オーケストレーションに役立つ理論を学ぶ

ストリングスのカリキュラムでもお伝えしておりますが、クラシカルな楽器編成で上手にアレンジできるようになりたいならクラシックの理論を学ぶのがイチバン。
ここでは、オーケストレーション上達に役立つクラシックの理論とその活用法をまとめました。
1)和声学を学ぶ
クラシックにおける基本中の基本ともいえる和声。
美しいハーモニーとその進行、各声部の自然な流れを身につけるために必要な知識と技術たくさん詰まっています。
とくにストリングスや合唱などのアレンジ力を高めるのに効果的ですが、オーケストレーションにおいてもこの和声学が非常に役立ちますので、勉強しておくことをオススメします!

2)楽器法を学ぶ
オーケストレーションの第一歩は楽器法から!
オーケストラで使用する各楽器の構造や特性、音域から得手不得手まで、必要な情報はすべて学ぶことができます。
楽器のことを知らずしてオーケストレーション上達はありえませんので、まずはしっかり楽器法を学びましょう。
楽器法は管弦楽法の理論書の前半部分に書かれている場合がほとんどです。
後述の管弦楽法の学習を進める上での前提知識となりますので、合わせて学んでいきましょう。
なお、ストリングスやホーンセクションのカリキュラム冒頭でも、それぞれの楽器法について解説しております。
そちらも合わせてご活用ください!
3)管弦楽法を学ぶ
和声を学び、楽器に対する知識も深まってきたところで、いよいよ本格的な管弦楽法について学んでいきましょう!
各楽器の特徴を活かした組み合わせ方、シンプルな四声体和声を拡大して壮大なオーケストラサウンドへ仕上げていくためのテクニックなど、さまざまなテクニックが学べます。
4)スコアを片っ端から分析する
前述の1)〜3)のステップで学んだ知識を総動員しながら、既存のオーケストラ楽曲のスコアを片っ端から分析してみましょう。
実際にDAWに打ち込んでみるのが効果的ですね!
まずは、古典派の作品(ベートーヴェン・モーツァルトなど)の作品から着手するといいと思います。
年代の新しいものほど複雑なオーケストレーションになっていきますので、初心者は古いものから順番に着手しましょうね。
※ちなみに、オーケストレーションの神様と呼ばれるラヴェル先生ですが、彼のオーケストレーションは規模が大きすぎて初心者が学ぶには無理ゲーすぎます。ご注意を!
STEP2:オーケストラ楽器を体験する・体感する

座学での学習がある程度すんだところで、今度は実際にオーケストラを聞きに行ったり、楽器を触ったりして、オーケストラ楽器を「体験」「体感」してみましょう!
5)生のオーケストラを聴きにいく

生の演奏を聴きにいくことで、各楽器の演奏の様子やサウンド感をイメージしやすくなります。
というか、そんなこと抜きにしてもメチャメチャ感動します・・・!!
現在は外出自粛中で直接会場へ行くことはむずかしいかもしれませんが、最近はコンサートのライブ配信も盛んに行われているようです。
とくに新日本フィルハーモニー交響楽団さんは、マルチカメラ&ハイレゾ配信というなかなか贅沢な仕様での配信も行っているようですので、超オススメです!
6)奏者さんの友達を作る

音大や専門学校に通うメリットのひとつに、あらゆる楽器専攻の人とお友達になれるところがありますね!
(後述する、アマチュアオケや吹奏楽団への入団も良い方法です。)
奏者さんの友達を作ることで、リアルな演奏の様子を間近で見せてもらうことができますし、楽器に関する基礎知識をレクチャーしてもらうこともできます。
持つべきものはプレイヤーの友達ですね!
7)管弦打楽器すべて一通りさわってみる

最低でも、「金管」「木管」「弦楽器」「打楽器」の4カテゴリをそれぞれ1種類ずつ、実際にふれて演奏の感触を確かめてみることはとっても重要です。(可能ならオーケストラ楽器をすべて体験できたらベスト!)
最近は、プラスチック製の管楽器など、安価だけど構造はホンモノの楽器と変わらない楽器も手に入るようになりましたので、上手に活用しながらできる限りたくさん楽器に触れる機会をつくっていきましょう!
STEP3:実地訓練でアウトプットする

いよいよ最後のステップ、実地訓練。
なにごとも現場に勝る学びはありません!
ここまでに得た知識を机上の空論で終わらせないためにも、実地訓練にどんどんチャレンジしていきましょう!
8)オーケストラ、吹奏楽団に入団する

アマチュアオーケストラや吹奏楽団に入団することは、オーケストレーション上達のためにぜひオススメ!!
なにせ、STEP2〜3のすべてを一気に経験することができますからね。これほど効率的な訓練の場はほかに思いつきません。
ぼく自身も小中高と吹奏楽部に所属していましたが、そのときに得た経験が現在のオーケストレーションスキルに役立ちまくっていることはいうまでもありません。
コロナ収束後は、即座にアマチュアオケ・吹奏楽団に入る!
くらいの勢いでよいかと思います。
9)指揮を経験する

オーケストラや吹奏楽団を指揮してみるのもとても良い経験になります。
奏者として参加するだけだと、どうしても自分のパートだけにとらわれがち。
一方、指揮者の立場ならオーケストレーション全体を俯瞰してみることができるので、アレンジの構造を把握しやすくなります。
スコアリーディングの実地訓練にもなりますしね。
こちらもアマチュアオケや吹奏楽団に入ることで簡単に経験できますのでオススメです!
10)レコーディングで大失敗する

多くのプロが口を揃えていうことですが、レコーディングで失敗することは、オーケストレーションスキル向上のための荒療治として一番効果があります。
(レコーディングでなくとも、自分の作品を生のオーケストラで演奏してもらう経験をするだけでもオッケー!)
いくら理論を学んでいても、生演奏してもらったらイメージどおりに鳴ってくれなかった・・・なんてことは珍しくありません。
多くのプロがこの経験を乗り越えてオーケストレーションの技術を磨いてきました。
できるかぎり早い段階で経験しておくことをオススメします!
こちらもオケ・吹奏楽団加入でチャンスが身近になりますので、チャンスがあれば臆せずチャレンジしていきましょう!
まとめ
というわけで、オーケストレーション上達に役立つ10のヒケツ、ご紹介しました!
今日ご紹介した10の項目は、ぼくがこれまで実践してきた中でとくにオーケストレーションの学習に役立ったものばかりです。
ぜひ参考にしていただければ幸いです!
ここまで読んだあなたへ
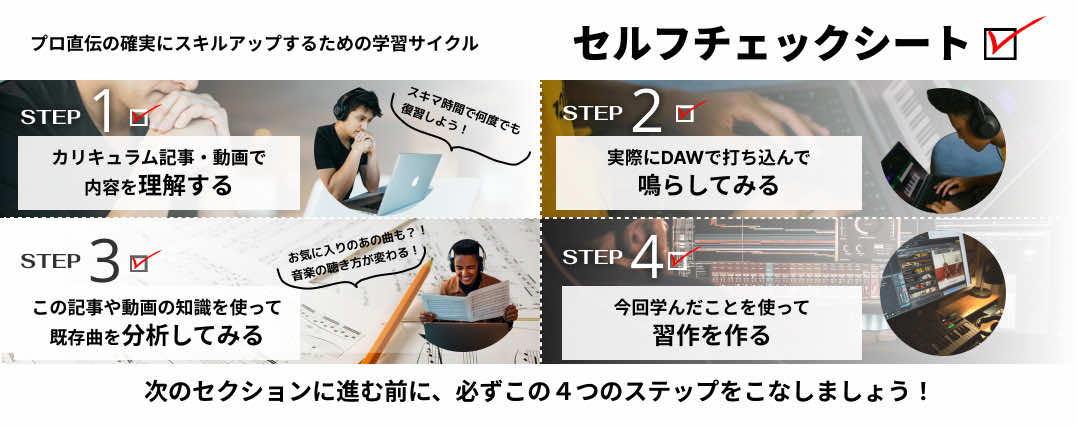 学んだ感想や習作をポストする!
学んだ感想や習作をポストする!
【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!
【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!
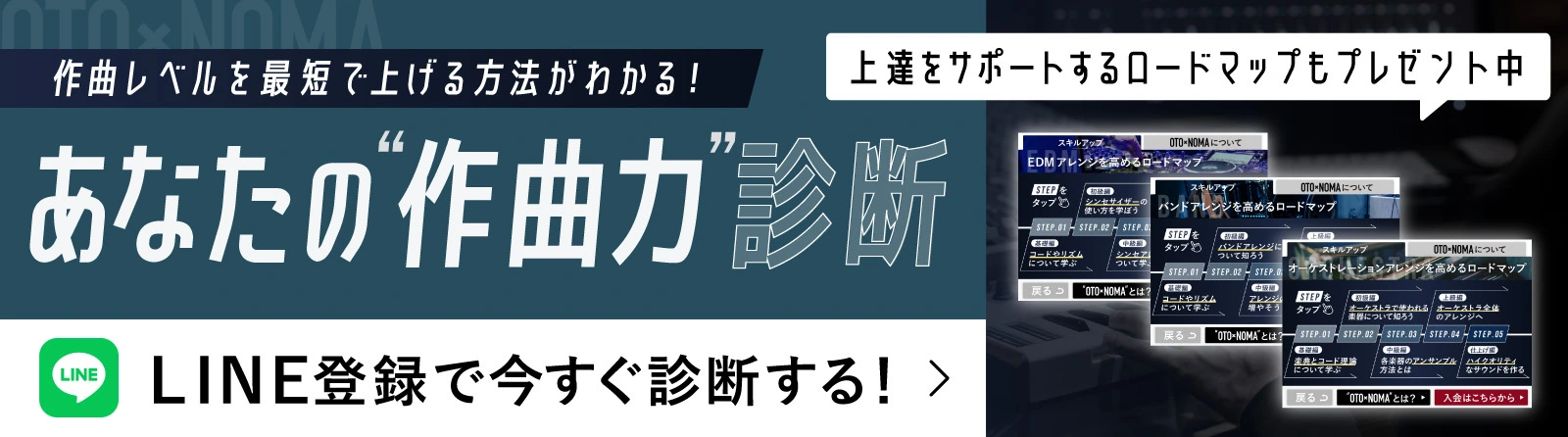
いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!