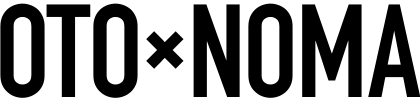【音楽ビジネス】Apple Music に Spotify。サブスク音楽配信がもたらす未来の音楽シーンを徹底考察!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介(@Ken_Inage)です。
Apple MusicやSpotifyなどのサブスク音楽配信。
読者のみなさまの中でも、作品を配信されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、これらのサブスク音楽配信の普及によってこれまでの音楽シーンの常識が大きく変化しています。
これから音楽シーンはどうなっていくのか?
今日はそんなテーマで考察していこうと思いますので、ぜひお楽しみください!
Apple Music に Spotify。サブスク音楽配信がもたらす未来の音楽シーンを徹底考察!

前提知識:サブスクの収益はどう分配されてるの?
まずは前提として、サブスクの売上がクリエイターにどう分配されているのかをお話ししておきますね!
みなさんご存知のとおり、サブスクは定額制聞き放題サービス。
従来のようにCDが何枚売れたとか何回DLされたとか、楽曲の売上がそのままクリエイターに支払われるわけではありません。
ではどうなっているのかというと、再生回数に応じた分配となっています。
例えばApple Musicの場合1再生あたりおよそ1円がクリエイター(原盤保有者)に還元される仕組みになっています。
自分の曲が1回再生されるとおよそ1円がApple社からもらえるということですね!
(ちなみにSpotifyの場合は1再生あたりおよそ0.6円とのこと。)
つまり、サブスクで1万円の売上をつくりたいならガンバって1万回再生を目指せばいいわけです。すごーくシンプル!
まずは前提知識として、このことを頭の片隅においといてください!
「ヒット曲」はもういらない?サブスクがもたらす重大な変化。

サブスクの普及によって、これまで当たり前とされていた音楽業界の常識が根底から覆されようとしています。
それは、「ヒット曲」を生み出すことの意義が消滅する!ということです。
そう、もう「ヒット」そのものを目指す必要がないのです。
「いやいやちょいまて!おれはヒットさせたいんじゃ!売れたいんじゃ!!」
そんな方もいらっしゃるかと思いますがご心配なく。ちゃんと売れます。
要は、
わざわざ「ヒット曲」を目指さなくても、十分「売れる」ことができるようになりましたよ!
ということなんです。
・・・・・・・・・。
はい、意味がわかりませんよね(笑)。
意味がわからなくて当然。それが「常識がくつがえる」ってことなんですから。
というわけで、その仕組みをわかりやすく解説していきましょう!
最近、いわゆる「ヒット曲」を目指す意味が薄れてきてますね。
理由は、サブスクの普及でだれでも簡単に全世界配信できるようになったから。
国内でヒット出すより、世界中のコアなファンを作った方が結果としてたくさん聞いてもらえる。
ニッチな曲でも勝負できるチャンスが増えたんです。(続
— 作曲家・稲毛謙介(イナゲケンスケ) (@Ken_Inage) March 11, 2020
理由その1:ニッチな曲でもちゃんと「売れる」ようになる!!

まずひとつめの理由は、ニッチな曲でもちゃんと「売れる」ようになるということです。
その背景には、サブスクのとある大きな特徴があります。
それは、「だれでも簡単に、しかも自宅にいながらにして”全世界配信”できちゃう」ということ。
パッケージ販売のときには考えられなかったことですが、サブスクなら簡単に全世界配信が実現できてしまうのです。
では、なぜ全世界配信できるようになるとニッチな曲でも売れるようになるんでしょうか?
世界市場に目を向ければ、市場規模が段違い!
例えばあなたが、100万人のファンを作ろうとします。
これを日本国内だけで獲得しようとした場合、日本の総人口に対してざっくりと1%の人から支持を得る必要があります。
人口の1%、すなわち100人に1人はあなたの音楽の熱心なファンになっていただく必要があるんです。
これって、かなりハードルが高いこと。
少なくとも、100人に1人のファンを獲得するには自分がやりたい音楽はおいといて、まずは「万人ウケ」する楽曲をつくらんと話になりません。
リスナーさんの反応を見ながら、いわゆる「売れ線」の曲を作りつづけないと、国内だけで100万人のファンを作るのは難しいでしょう。
一方、海外に目を向けてみるとどうでしょう?
全世界にはおよそ80億人もの人口がいます。
同じ100万人のファンを作るとしても、日本国内だけならば全人口の1%もの人から支持を集める必要がありましたが、全世界の人が相手ならば、その割合は大きく下がります。
どれくらい下がるかというと、およそ0.01%です。
そう、1万人にたった1人だけ自分の音楽を熱心に聞いてくれるファンを作ればいいんです。
この割合ならば、ムリに「万人ウケ」する音楽をつくらなくてもよい。
むしろちょっとニッチなくらいでも十分にチャンスを狙える割合です。
サブスクの普及によって、
- 簡単に世界展開を狙えるようになったこと
- 市場がバクレツに広がったこと
- それによってニッチな楽曲でも勝負できるようになったこと
これこそが、「ヒット曲」を目指さずとも「売れる」ことができる1つめの理由です。
理由その2:一時的なヒットより、長く愛される楽曲の方が結果的に「売れる」

サブスクのもう1つの特徴は、すべての音源データが「クラウド上にある」ということです。
リスナーさんは、いつでもどこでも聞きたいときにネットを通じてクラウド上の音楽ファイルにアクセスできます。
CDはおろかデータすらも所有する必要がありません。
今手元にもっていない楽曲でもおかまいなし!
- 思い出の場所におとずれたとき
- 急に青春時代の聞きたくなったとき
- 街なかで気に入った曲をみつけとき
いつでもどこでも、自由にクラウドにアクセスして聴きたい音楽を聴くことができるわけです。
もしかしたら、特定の楽曲を指定することすらしないかもしれません。
その時の気分に合わせて、AIがオススメしてくれるプレイリストを聴く。
知らない曲に出会うチャンスもぐっとひろがるし、選曲の手間もない。
そのような新しい音楽の楽しみ方も広がっています。
となれば、人は自ずと「ヒット曲」よりも「自分の好み」で楽曲を選ぶようになることは容易に想像がつきませんか?
すくなくともぼくがApple Musicで音楽を聴くとき、ヒットしたかどうかに関係なく、自分の好みで楽曲を選んでいます。
仕事上必要があってヒット曲を検索することこそあれど、プライベートで音楽を聴くときは完全に好みで選曲してます。
大事なのは「ヒットする」ことよりも「選んでもらう」こと
この時代の流れを考えるなら、「ヒットする」ことよりも「選んでもらう」ことの方がよほど重要です。
どんな理由であろうと、自分の曲を再生してもらうこと(=選んでもらうこと)さえできれば、再生回数は伸び売上があがっていくわけです。
リスナーさんの「お気に入り」になることがヒットを作るよりも重要だということがよくお分かりいただけるかと思います。
ならば、一時的なヒットをとばすよりも、生涯にわたって長く聞き続けてもらえる楽曲の方が結果的に大きな収益につながっていくことは明白。
1年間で100万回再生されても、その後失速してしまっては意味がない。
むしろ1年間に10万回でも向こう数十年にわたって聞き続けてもらえる音楽を配信できれば、結果的に収益は大きくなりますよね。
サブスクの登場で、音楽にもいわゆる「ロングテール戦略」が求められる時代になってきたと考えてよいでしょう。
昨日お話しした「ヒット曲を目指す必要性」にも通じるけど、
今の時代目指すべきは、一過性のヒットではなく「ロングテール」戦略です。
サブスクは再生回数によって売上がカウントされるシステムなので、
一時的にドドッと人気出るより
なが〜く聞き続けてもらったほうが有利なんです。(続
— 作曲家・稲毛謙介(イナゲケンスケ) (@Ken_Inage) March 12, 2020
まとめ
サブスクの登場によって、「ヒット曲」を目指す理由がいかに減ってきているのかがお分かりいただけたかと思います。
ある意味、「ヒットの定義が変わった」ともいえるかもしれませんね!
我々クリエイターにとっては、売れ線の曲をガンバっての書きつづけるよりも、自由に音楽を表現できるほうが人生も楽しくなるはず。
しかもそれで大きな収益も得られるとなれば、サブスクの普及は歓迎すべき時代の流れだといえるでしょう!
時代の流れをしっかり押さえて、ともに楽しい音楽人生を歩んでいこうじゃありませんか!
ここまで読んだあなたへ
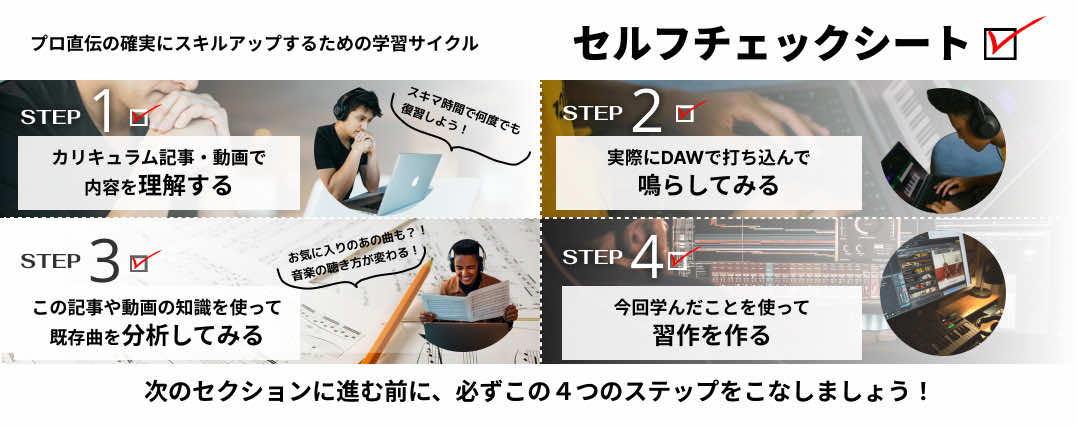 学んだ感想や習作をポストする!
学んだ感想や習作をポストする!
【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!
【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!
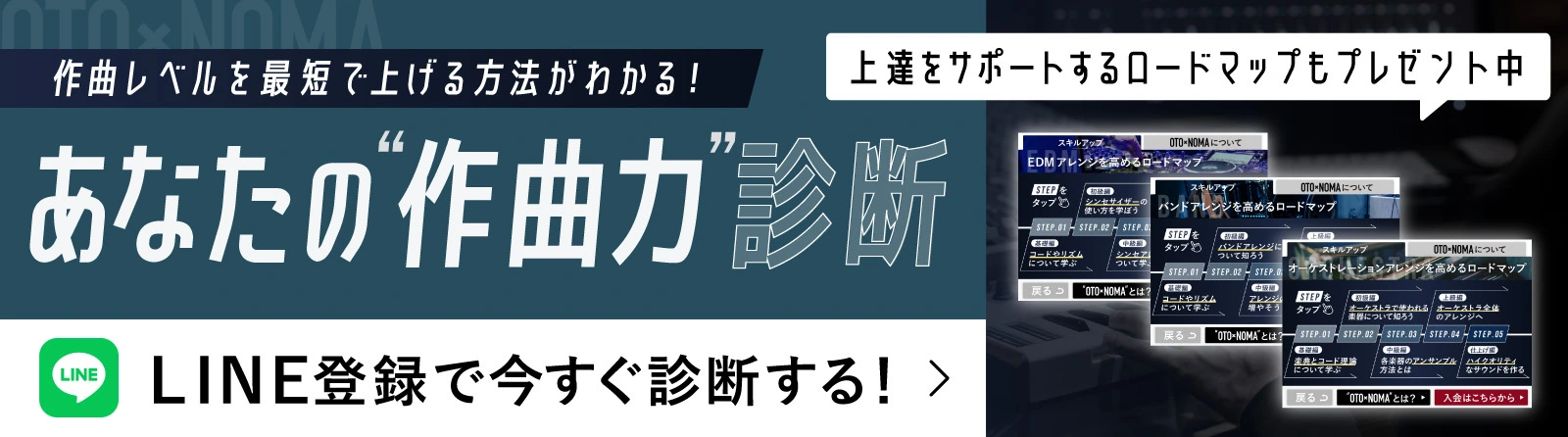
いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!